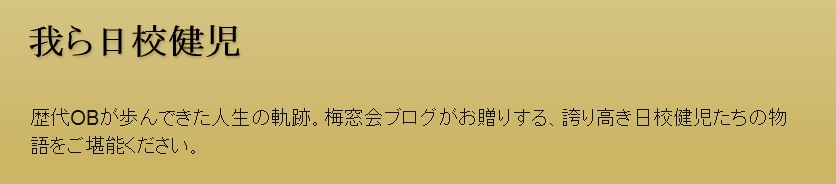冬・岡谷への復員
両親が当時工場疎開で岡谷におりましたので、兎に角一応父母に元気な顔を見せて身の振り方はその後のことだと、一人新宿駅より中央線で岡谷に向かったのです。列車は復員者や疎開先からの引揚げとか食料買い出しの旅行者で超満員、お陰で車窓から半身はみ出る者が鈴なりの騒ぎでしたが、次第に乗客も減ってゆき、トンネルを次々に通過する程には機関車の煤煙に煤だらけにされながらも、やがて岡谷に辿り着いたのです。

氷結した厳冬の諏訪湖
降り立ってみると一面銀世界、凍て付く寒さの中でした。父のいる東京発動機の社宅は岡谷の街から徒歩二〇分ほど坂道を上った高台で工場疎開敷地内にあり、昔、木曾義仲四天王・今井四郎の子孫の住む“今井の郷”と云はれる一帯です。昔は広々とした馬の放牧場だったとか。でも冬中はずっと四〇~五〇㎝の薄雪に覆われ身を切る寒さ、水道も出っぱなしにして置かないと忽ち凍結してしまうといった所ですが、上を見れば峠の上でスキーを、遠く見下ろす諏訪湖ではスケートも楽しめるといったふうで、塩尻峠の麓に広々と展開する丘陵地帯でした。また上諏訪温泉までは自転車・バスで一息、そこの市民浴場「片倉館」で半日温泉を楽しむことも出来ます。地元会社の諏訪製糸社が市民に提供する総大理石造りの素晴らしいローマ風呂で、ブロンズ像とか壁面彫刻なども配置され雰囲気一杯と言うところです。気候的には暮らしにくいようですが、一面楽しみも結構あるところです。

当時と変わらない上諏訪・片倉館のローマ風呂
冬と炭焼
地元では冬を越すのに養蚕用の桑の根が専ら炬燵の熾きに使われ、煙も出ず火力も結構あるのでそれはそれで好いのですが、矢張り疎開してきた都会の人には木炭が無いのは辛く、そこで八ヶ岳から伐りだして山のように貯蔵してあった会社の薪を使い、父と相談して地元山男の今井今朝治爺さんに炭焼釜の要領を習い、会社構内に所謂石釜を構築、雪の降る日(註1)を選んでは三日間、昼夜ぶっ通しの炭焼きも新鮮で、それ程辛くも感じず結構良質の炭が上手(註2)にできました。早速社宅の人たちにも頼まれては五釜ほど焼いて配り感謝されたりして冬を過ごしたと云う訳です。

冬の八ヶ岳
註1:雪の降る季節を選ぶのは、炭が焼き上がった直後に釜の天蓋を払い、降り積もった三〇~四〇㌢の雪を一気に釜の中に落とし込めば、丁度好い釜内消火・冷却剤になり且つ硬い良質の白炭が得られるからです。
註2:炭焼のコツは、ご存知のように、柔らかい黒炭には松・桧材を、堅い白炭には硬質の楢・樫・椚材など木材種を兎に角均一に選ぶこと、石釜の管理では土管利用の排気管から出る白い煙の濃さと量の状態から蒸し焼きの進行と釜内温度の適否(千℃以上の比較的高温)を判断し、釜焚き口の火の色と開き具合を如何に忠実に管理するか、そして最後に消火・冷却時間のとり方に係っている訳です。柔らかい黒炭はゆっくり、硬い白炭は急激に雪などで冷却するのがコツです。
釜前で思うこと
燦々と雪降るなか釜前に天幕を張り、しゃがみ込んで炭焼釜の焚き口をじっと見詰めて居ると、ふと浮ぶのは、想い出も遠く何処の天地でか亡き人と散った「同期の桜」の面影。終戦と共に忘れ去られた彼等の魂は今何処の地のもとで、それとも風に吹かれて寒々しくも流離わねばならないのであろうか?と。だから焼きあがった炭を手に採り乍ら、彼等の魂もこの炭の暖かい隙間にひとつひとつ仕舞い込んでやれば、次に火を熾したときにはきっと真っ赤に燃えて「暖かい!」と喜ぶのではと。せめて一本の炭の中でも好いから、皆に忘れられないような安住の地を見つけ、話も聴いて上げられたら?等々ふと切ない思いに囚われてしまうのです。

諏訪湖の神渡
岡谷の冬は永くて寒い。そして地元の人が「春は湖面からやって来る」と言うように、年を越して一月の所謂「神走り」なる雷鳴と共に始まった諏訪湖の全面結氷も、三月三日の天皇誕生日(天長節)の頃ともなるとやっと緩み始め、春の兆しを感じるようになります。一方、峠に近い今井の郷は三月末になっても未だ雪が残り、地中の温もりも懐かしく足の裏で感じる馬鈴薯の畝造りや施肥など、じりじり待った春明け一番の農耕が本格的に始まるのは、未だ四月半ばを迎えてからのことです。
心の遍歴
そこで話を少し戻しますが、敗戦から岡谷に向かいそこで暫く暮らすことになった当時の心の遍歴を少々お話します。
私が敗戦で荒廃し尽くした街に帰還兵として降り立ったのは十二月初めのこととお話しましたが、戦争責任(連合軍の言う所謂「戦犯」)の追究につきましては、既に九月初旬より始まる第一次から第四次に亘るA級戦犯、更に十一月初旬よりはB・C級戦犯者リスト並びに処刑発表が次々と街に流され、今まで下火であった、帰還兵に対する世間の風当たりもそろそろ厳しくなり始めた頃で、革鞄と五〇キロ近い衣嚢を担ぎ、上等飛行兵曹の海軍軍服を着ていた私も新宿駅辺りからはそうした厳しい視線・応対を時に感じる中での帰還でした。しかし岡谷に着いてからの身内は勿論、会社周辺、更には地元今井の方達に到るまで、その応対は暖かく、好意と労りに満ちたもので、敗残の兵として多少打ちのめされた意識下での私には意外なものでした。

終戦直後の新宿駅周辺
私達は三人男兄弟でしたが、長男は前にもお話しましたように陸軍幹部候補生から豊橋の予備士官学校を経て、任官後は豊橋の機甲師団で中隊長となり、本土決戦に備えての飛行場建設任務中に終戦を迎え無事復員、旧勤務先の富士電機社大阪支店にも無事おさまり既に出社しており、また身体の稍々弱い次男は東京高等農林を卒業後、飯田の農業高校教諭に在職中で、二人とも岡谷には不在でしたが、若い盛りの男兄弟三人が何と全員無事戦災を免れたとは、当時の大量の戦死者と敗戦という情勢下では希有な幸運であるとして、会社や地元の人々からも大変祝福されたものでした。

焼け野原の東京
勿論私達一家族としてはその様な周囲からの好意は素直に有難く戴いておりましたが。一方、しかし当時の私の心情の中心では「生かされていることへの感謝と悦び」を実感していたとはいえ、未だ心の一隅では突き詰めるべき今一つ違った世界の問題が座り込み、稍々もすると、総じて気が重い状態だったわけです。時に擦れ違った知人を見忘れ、気が付かず通り過ぎたと笑われ注意されたりでした。これからの生き様を決めるうえでも、この敗戦に到る四年間の自分と周辺で起きた事柄をどう見詰め直し、次の一歩はどの様に踏み出したらよいのかとの思いが、絶えず頭の一隅を占めていたのです。
海軍に在隊中の四年間、変わらず私の胸をずっと占め続けた思いは、出発の処で申しました様に、「この制空権の戦いこそ国運を賭するものであれば、其の勝利の為には寧ろ一飛行兵として参加し、そして全力を尽くして勝ち抜き生き抜く」覚悟でした。それが航空隊に於ける日頃の技術・胆力修練の過程であれ、熾烈な死をも賭した戦場であれ私にとっては一貫して変わらぬものであったし、他のパイロット達全員、彼等もまた私と同様に戦場での死闘を当然のことと意識し、尚且つ勝利を信じて志願した者達であれば、共通した覚悟だったと思います。
そうした共通の覚悟を持ち、訓練にいそしみ励み、一途に国を信じて闘って死んでいった者、或いは生き残った者、一体何がこの生死という個人にとっては途方もない命運を差配したのでしょう?闘かったら必ず死ぬ?とんでも無い間違いです。死んでは負けですから必ず勝って生き残らなければならないし、その為にも徹底的な訓練と、より優れた装備性能の保障こそ決め手になります。そして少なくも装備に関する限り国はそれを怠ったと言えます。即ちこの戦いの勝敗を決したのは、寧ろ「人命尊重の如何」にこそ主因があったと思います。機体の臨戦性能、銃器・装甲の改善、銃後の大量生産方式の確立、最前線での航空戦闘方式の見直し改善等々です。ハワイの敗北から起ちあがり、六ヶ月の徹底的な航空戦略の見直しを経た米軍航空戦隊の反撃に対し、緒戦の奇襲勝利に奢り人命の尊重意識に注意を怠った日本の安易な六ヶ月がその後の勝敗を決したと云っても間違いではないと思います。

世界最高の性能を誇ったゼロ戦
例えば、未熟なパイロットを主体とする米空軍の戦闘作戦では、パイロットには編隊飛行と一撃主義を徹底したことです。一戦闘では複数交戦を絶対避け、情報戦に徹して味方にとって最も有利な態勢からの一撃で任務を完了し、戦果の如何を問わず決して深追いはしないという方式です。搭乗員の未熟をカバーし且つ被害をも最小限度に留めながら、数量・物量面での有利さをフルに活用して最大の戦果を挙げることに徹底したわけです。日本空軍は世界に冠たる性能を誇るゼロ戦を保有しながら、以後改善に遅れを執り、数量・装甲の劣勢は腕を過信した深追いの戦術でカバーしようとしてみすみす有能なパイロットを次々と犠牲とし、以後主要海戦・空中戦の作戦主導権はアメリカ側に奪われ敗戦を重ねる結果を招いてしまった訳です。以下参考までにミッドウエー海戦以降の主要作戦を列挙します。
昭和十七年五~八月:珊瑚海海戦。
昭和十七年六月:ミッドウェイ海戦、
昭和十七年八月~十八年十二月:ソロモン諸島海戦
昭和十七年十月:南太平洋海戦、
昭和十八年二月:ガダルカナル島撤退、
昭和十九年二月:ラバウル航空隊撤収
昭和十九年二月~六月:トラック・マリアナ沖海戦、
昭和十九年六月:サイパン・テニアン・ガム玉砕
昭和十九年十月~:比島沖海戦、
昭和二十年一月~:特攻作戦開始、
昭和二十年四月:沖縄戦
以上は四年間に亘る海軍生活を通して私が戦争と向かい合い、
そして経験したものに対する感想の一端です。
敗戦から復興へ
以上敗戦への想いを縷々綴って参りましたが、これは実は既に次の復興へのステップが如何なるものか「希望の光」を模索する国全体としての反省課題でもあり、そして思考構造を「徹底した人権と科学重視社会の実現」に如何に効率よく切り替えて行けるか?とこれこそが、当時敗残から起ち上がろうとしている日本にとって突き詰めた処の課題であったと思います。

終戦直後の闇市・焼き鳥を焼く人々
一方、個人的な問題ではありますが、四年間の海軍生活中、私は国内航空隊勤務に終始したのですが、他方前線各地の総てが不利な戦況下であり乍ら、尚且つ次々と戦場に赴き闘いに散って往った余りにも多数の同期の桜への鎮魂の想いは気重く忘れ難く、斯く心の負担を背負った私にとって、実はこの寒くて長い冬の時間は、突き詰めた想いを纏める為には大変貴重なまた大きな癒しにもなりました。前線に向かえばこそ、忽ち熾烈な戦いの末に次々と帰らぬ人となっていった予科練・飛練仲間、勤務上様々な出会いを持った亡き上官・戦友達の無念と償いは如何、人の生死を分かつものは一体何なのか?挙げ句の果ての敗戦と、その荒廃し尽くした日本の前途のこと!この敗残の国土を、必ずや次は生気に満ちた新生へと再建せねばならないがどうやって!等々の思い。次の時代こそ日本の勝利を実現するのだと。それが生き残った私達の仕事なのだと。想いは積るばかりでした。
読書と模索
吹き渡る風も冷たい高原を歩きながら、今この自然の懐、広がる大地に立ち、考え模索することは数限りなくありました。そして納得のいく解答を求めて嘗ての書を読み返し、或いは新たに読み加えるべき数々の書を手元に積み上げたのです。

霧ヶ峰高原
大筋としては海軍入隊前に読んだ「昭和史」・「偉人伝」・「武士道葉隠れ」に始まり、新たに哲学書の数冊【ニーチェの「ツアラトウストラ・序」(自己超克の哲学)・ベルグゾン(生命の哲学)・西田幾太郎(善の哲学)】及び日本文学全集三六巻。これら大分冊だが最終読み終わりは日本文学全集を以て六月一杯で仕上げとしました。日本文学全集・ニーチェの「ツアラトウストラ序」は長男の蔵書、ベルグゾン哲学・西田幾多郎の「善の哲学」は岡谷の古本書店で見つけて来たもの。これら書選択の経緯は、「武士道葉隠」の根幹精神(名言1.5.7.8.9.⒓)が、ニーチェの「死の哲学」とも言われる自己超克の哲学で主張される処、即ち人間本来あるべき理想的生き様とよく一致し、更にはベルグゾンの「生命の哲学」・西田幾多郎の「善の研究」で主張される哲理にも、洋の東西を問わず相通ずる理想を見たからです。

西田幾多郎著『善の研究』
結局私自身の生き様は、ニーチェの「超人」、ベルグゾンの「生命」、西田の「善」で共通して説かれる《超克》こそ目標と断じての再出発となった訳です。過去、学校で或いは海軍で鍛えられ磨き抜かれて、今あるがままの自然体、自信と決意を以て一向に前向きに生きるのみと断じ得て、最早無用に過去は振り返らないと。書による反省、書による確信、それが行動への自信となり、過去を振り切って新生の第一歩となったのです。
ニーチェの自己超克の哲学について
「神は死んだ」
有名な言葉である。ドイツ人ニーチェはキリスト教に代わって自己超克という新しい生き方を示した。これは人類に新しい生き方について刺激を与えた。多くの人は古い認識に固執し、この結果事を処するに目先の恐怖心・執着・遅疑・焦燥等々感情や勝手な想像、又は財産など喪失感に拘り、目先が暗くなり事の真実を見失い、直感的に己の優れた能力・感性力を発揮できないで居る。本来自己の所有する勝れた能力・感性を常日頃磨き、自己の夢実現に向かい新しい生き方の切っ掛けにすべきであると。
「超人」
昨日までの自分の中の世間性(常識)を超えて、自己本来の能力・感性に目覚め、絶えざる自己超克を為し遂げる者。大地の如しと?この「大地の如し」で思うことは、岡谷の大地で鍬を振るいながら素足の下に感じた自然の大きさ、暖かみへの感動です。それは自然と一体になった自己認識です。
「遠近法的思考」
認識修練を積み重ねるとき、人はより近くも遠くも(例えば日本と海外。自己と他。現代と将来等々)が同様にしかも同時に確かり見えて来る。

フレードリヒ・ニーチェ
再生へ一歩
かくて、私の心は次第に決まり、今やるべき目前の事にこそ力の総てを集中して行こうとの心境にあったのです。そこからやがて生まれるものを待つという心境です。行動面では雪の散散と降る中での炭焼きの新鮮な悦び、会社が開発中の農耕用トラクターエンジンの試運転・改良への打ち込み、春を迎えては大地の温もりを感じながら振る一鍬々々の手応え、光り輝く収穫物をはじめ太陽の下あらゆる生命力の息吹きを見詰め、雨に風に雷光に打たれながら「我此処に自然と共に生きる」と無言ながら胸に響く感動の一言。
塩尻峠を越えて獣道にふみいれば、ぼや址に暗く静まりかえる沼地周りでは、熊か猪か?獣達の秘かにこちらを窺う気配に、本来なら不気味さを感じるところも寧ろ生きるものへの懐かしささえ感じ、再び戻った峠の陽光の下では、群れる鳥の平和な囀りに包まれ、やがて雲雀啼く今井の郷が足下に見えてくるとき、鍛えられた体力、集中力そして新たな人生へと挑戦の自信が全身に漲れ出て感じられる。そして学ぶ事への欲求も高まる。戦場の記憶も亡き友と共に徐々に遠ざかって往った。世界一流を目指した第一ラウンドの戦いが敗戦で終わり、次は確実に勝たねばならぬ第二ラウンドが始まったのだ。

第4回・後編 「春―田園交響曲」へ続く